ほとんどのテキストに載っていないと思われる、債務引受が出題されました
問題文には、承諾に関する、と書いてあります。4肢は債務引受の内容ではなく、通常の勉強範囲で、すぐに誤りとわかりますから、実質3択問題ということになります
初めて聞く単語や分野に遭遇した場合、勘に頼って選択するのか、何とか予測して一応の答えを導くのか二通りあります
多くの方が後者で、文章からヒントを探したり、言葉の意味を予想して解答するはずですが、どのように考えているのか人によって違いがあるかと思います。そこで、債務引受契約の1-3肢について、私なりにアプローチしてみます
まずは問題文。正しいものを選択しますので、1つが合っていて、反対に、残り2つは間違っているということ。当たり前のことだけれど、焦っていると忘れがちです
次に、選択肢を確認すると、3つとも同じような構成になっていて、登場人物としては、当事者(債権者・債務者)と第三者の3名が出てきます。第三者と当事者が債務引受という契約を締結するケースで、もう片方の当事者が承諾をした際の話です
ここまでは分かるとして、債務引受契約という言葉がわからないため止まってしまいます。しかし、今回の場合であれば、単語にばらして考えると、なんとなく理解できます
第一に、契約であるという点。文章からも分かりますが、2者間で行う契約行為ということです。そして、その契約というのは、言葉の通り、債務を引き受けるということだとわかります
登場人物が3人いることを確認していますので、想像しやすいです。何らかの、例えば売買契約を締結している方々を考えると、債務者が抱えている代金支払い債務を、誰かに引き受けてもらう契約を、債務者あるいは債権者と締結するものではないかと予想できます
これにたどり着けば、免責的・併存的にもあたりがつきます。引き受けた債務について、元の債務者の履行義務を免除するのか、継続させるのかということです
実際に当てはめると、1では第三者と債務者が契約を締結しています。債権者の視点から、承諾不要は明らかに間違いであると判断できます
2も同様の契約ですが、債権者承諾によって効果を発揮するかどうか。併存的なので、債権者の承諾はなくても困らないのではないか?とも思いますので、一旦保留で△にしておきます
最後は、第三者と債権者が契約をした場合で、1,2とは異なります。引き受ける債務について、債権者が主導権を握っていますから、債務者がその成否のポイントになるとは考えづらいです。仮に△と思ったとしても、2番との比較でこちらが誤り、2が正解と答えを出せます
ぱっと見でわからない問題に時間をかけるのはロスなので、一旦飛ばして、最後に時間があったら検討してみましょう
補足
厳密には、1肢は単に承諾が必要かどうかですが、2,3肢では、第三者に承諾した時点で効力が生ずるか、ということを聞かれていて、承諾した時点かどうかが論点になっていました。その点詳しくみてみます
組み合わせ的には、4つの場面が想定できます
併存的の第三者-債務者
併存的の第三者-債権者
免責的の第三者-債務者
免責的の第三者-債権者←今回出なかったパターン
※もちろん三者間というのもありますが、論点と関係ないので省きます
第三者-債務者だと、併存的では契約だけで効力発生(3肢の正解)するが、今回出題のなかった免責的のケースでは、契約だけでなく、債権者から債務者への通知をもって効力発生ということになります(免責的だと、当然本人が免除されたことを知らないと、客観的に見て、単に債務者が増えただけの状態で、併存的債務引受となんら変わりがないですから、通知をして債務者自身が免責されたことを知ることが必要ということでしょう。従来、基本的には通知なくても成立でしたが、法改正で要通知に変更されました)
今回は、ここまでの知識がなくても影響ありませんでした。免責的・併存的の違い、法改正への対応、効力発生要件等、細かいところは問われておらず、出題がストレートだったのでよかったですが、免責的の第三者-債権者において、契約時に効力が生ずる。併存的の第三者-債権者において、債務者への通知をもって効力を生ずる。あるいは、債権者ではなく第三者からの通知に変えるなどなど、変化球が混じっていたらだめでした
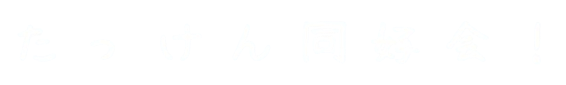
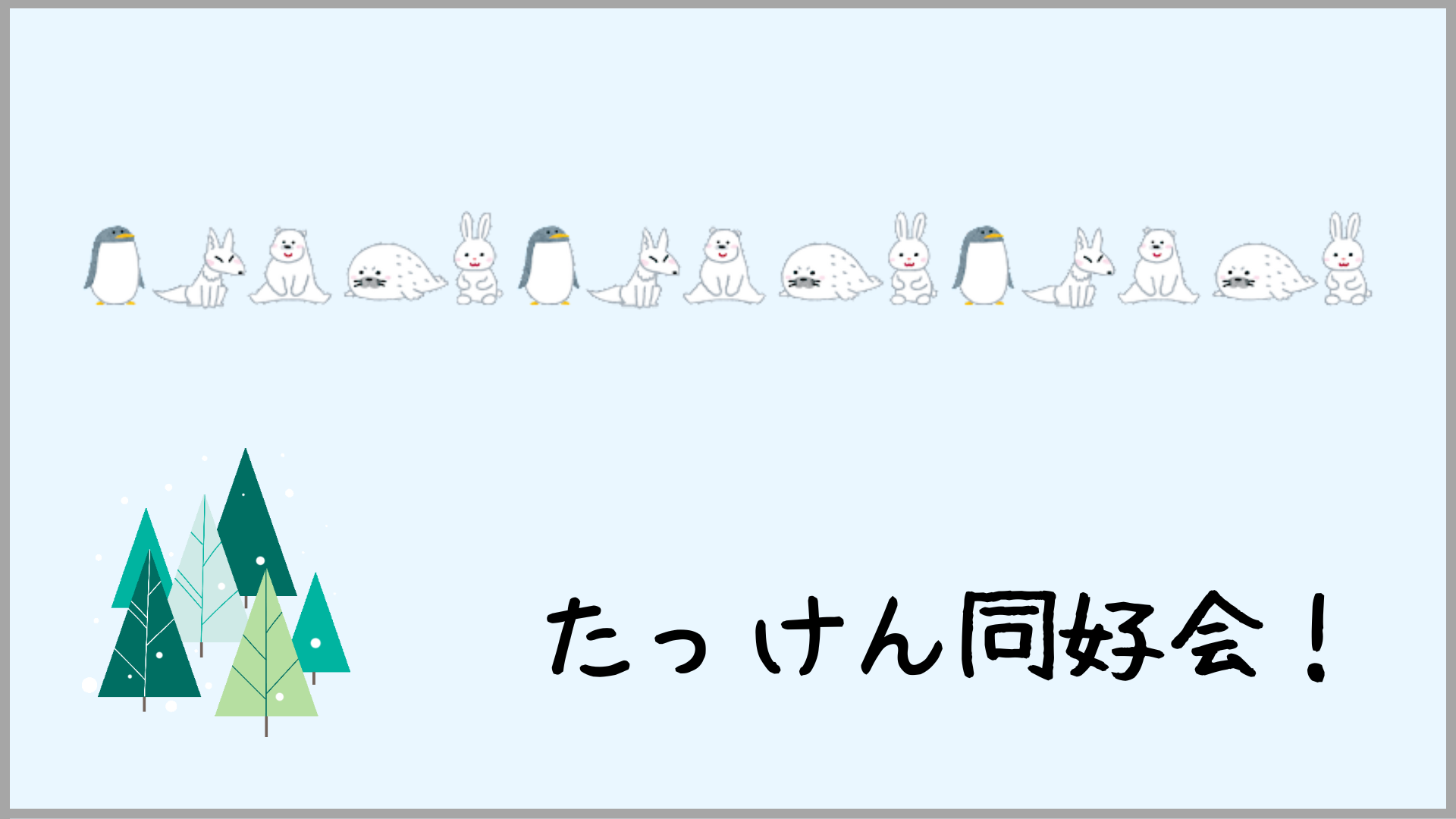
コメント欄 〈お気軽に投稿ください〉