ラッキー問題といわれている農地法が、突然難しくなったと話題になりました
ただ、平成26年試験の不正解肢の1つに丸々同じ内容があるので、正解できた方は意外と多かったかもしれません。令和6年試験時点では、ちょうど10年前なので、一般的な市販の過去問題集(直近10年分)を取り組んでいれば即答できます
停止条件付売買契約、仮登記、民事調停、連署など、農地法の分野では想定していなかった単語が出てきて焦ってしまいます。ほんとに農地法?権利関係じゃない?って感じ。肢の1つや2つ難しくて、正解肢は簡単とかならわかるけれど、4つとも難しい内容でした
4つ全部わからない場合のアプローチ方法を考えてみます。まずは、誤っているものを選択するということを確認します
そして、1-4肢の主要な論点を確認します
1:許可が必要かどうか
2:連署かどうか
3:数字が正しいか・賃貸借したとみなされるか
4:許可権者・解除等できるか
この中のどこが間違っていそうか検討しますが、2-4については、一定の場合を除き、という例外言及がありますので、この点に着目しましょう
○○を除きという一言がなかった場合、一般論として文章が成立していても、例外を排除できないため、不正解の文章と扱われることが多いです。例外への言及があるということは、もちろんその例外が論点となっていることもありますが、正しい内容である傾向にあります
例外の内容が重要であれば、そこが論点になることも十分考えられますが、農地法というマイナー分野で、原則についても初出?の難しい内容なのに、例外部分までさらに細かく知識を問うということは考えづらいです
一定の場合を除きという文言がないという根拠だけで、1を選択することはかなり危険ですが、2-4肢が正しい内容である可能性が少し高いということと、例外部分は読み飛ばして、文章を簡単にとらえて問題ないと判断できます
そこで、相対的に不正解の確率が少し高い1番について考えてみます
3条許可というのは、所有権移転で、4,5と違い農業委員会が許可権者ということは思い出せるでしょう。停止条件は権利関係で勉強していますので、3条許可が出たら契約成立という条件付きの契約ということまでは理解できます。条件が成就して契約となった暁には所有権移転登記をする、そのための仮登記に許可が必要かという話です
もし仮登記がわからなくても、3条許可の前に別途第一段階の許可が必要かどうかという構造に気づけば問題ないです
仮登記許可→3条許可
〇→〇
〇→×
×→(〇)
×→(×)
ダブルチェックの体制ということになりますが、問題の仮登記の許可権者と、3条許可の許可権者が同一(農業委員会)ですから、この二重のチェックはほとんど意味がなさそうなので、農業委員会による仮登記許可は不要ではないかと推測できます
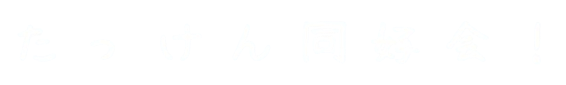
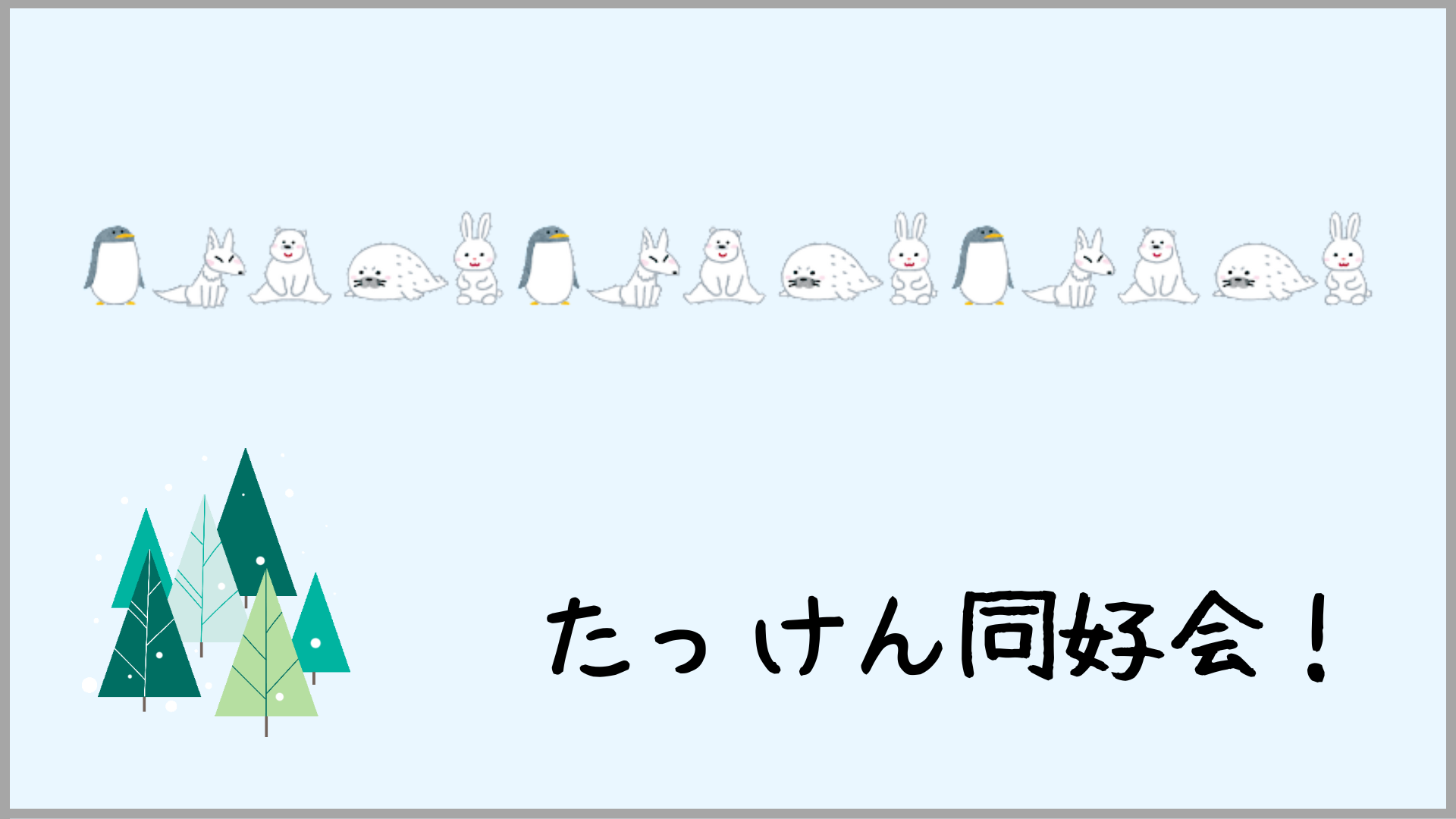
コメント欄 〈お気軽に投稿ください〉