法令上の制限は、基本的に以下の8問で出題が固定されていますが、その内1問はその他の分野となることがあります
都市計画法:2問
建築基準法:2問
盛土規制法(宅地造成等規制法):1問
土地区画整理法:1問
農地法:1問
国土利用計画法:1問
直近は平成29年試験で、国土法に代わり、その他の分野が出題されました。その前だと、25,26年(25年の前は20年まで遡ります。)、直近令和試験での出題はありません
平成30年までは、その他がない定形出題だとしても、問題番号と分野が絶対的に決まっておらず不安定?でしたが、令和に切り替わったタイミングで、問題番号・出題は固定化されました
問15:都市計画法
問16:都市計画法
問17:建築基準法
問18:建築基準法
問19:盛土規制法(宅地造成等規制法)
問20:土地区画整理法
問21:農地法
問22:国土利用計画法
となると、令和の宅建試験、今後その他の出題はないと考えてよいのではないでしょうか?
そもそも、なぜその他の出題があるのか。直近3回分のその他は、いずれも国土法の代わりに出題がありますが、代わったといっても、肢の1つは国土法です。国土法はその適用場面が限定的なので、あまり重要ではなく、テーマとして1題にするほどでもないということでしょうか(残る3肢も宅建業の必須知識とはいえないので、別に国土法でもいい気がしますし、いっそのこと、都市計画法3問に変更でよいのではないかと思います)
過去問は12年分や10年分が主流ですが、あと何年かすれば、平成25,26年の過去問はカバーされず、29年の1題だけになり、ゆくゆくは0問ということなってしまいます。そうはさせまいと、ここ数年のうちに出題されるのではないかという見方もできます
その他がでるかもしれないからといって、なにか対策できるわけでもないので、考えるだけ詮ないですが、許可権者は最低限(現実的な勉強範囲でいえば最大限でもある。)覚えておくことにします
(ちなみに、国土法がその他になって1/4に縮小したということは、あえて国土法を正解肢には持ってくるはずはなく、1/3に絞ることができる、と思いきや、平成25年試験では国土法が正解になっていました)
【注意事項】
・本考察は娯楽として捉えてください
・令和の宅建試験をベースにしています。遡っても平成27年からの“取引士”試験まで。26年以前の“主任者”試験は外しています
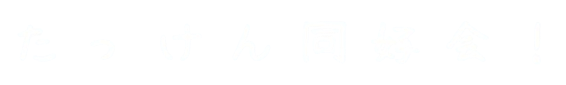
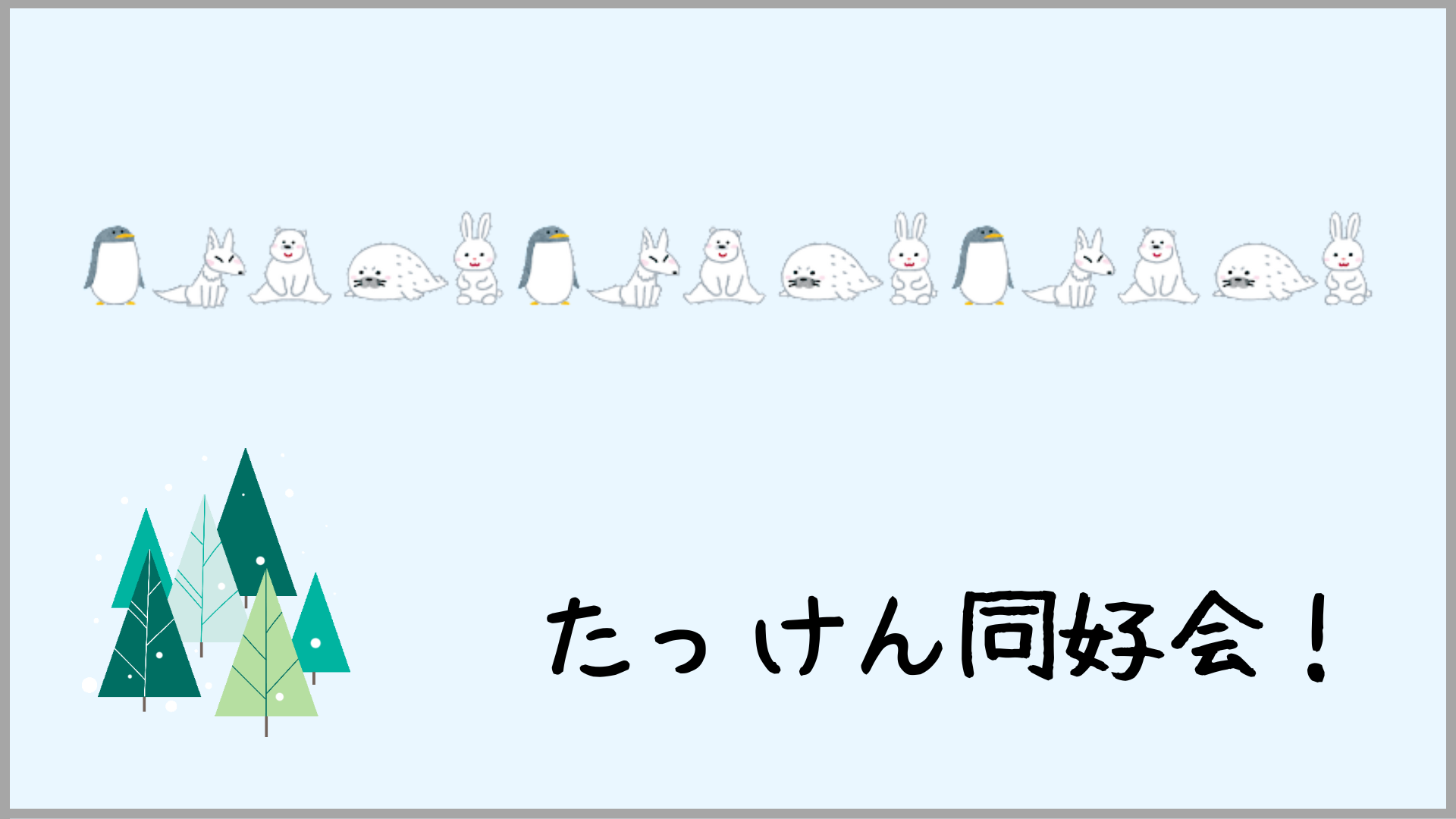
コメント欄 〈お気軽に投稿ください〉